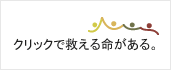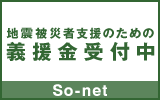野生の哲学 [社会]
皆様方のいつも温かいご支援を感謝いたします。
my challenger's log 一冊目は、
こちら
http://mwainfo.blog.so-net.ne.jp/
より閲覧願います。
野生の狼の強靭な生命力(WILD NATURE 地球大紀行)
『野生のオオカミ母子 厳冬のアルプスを生き抜く
イタリア・アルプスで命を落とした一匹のオスのオオカミ。
ボスであったそのオスを失ったメスのオオカミは、群れを追われます。
彼女には生きる理由がありました。彼女のお腹には6匹の小さな命が宿っていたのです。
たった独り、アルプスの厳しい自然の中で出産をし、捕食者たちから身を護り、獲物を狩り、子供た ちを育てなければなりません。
凍てつく雪と暴風の中で、危機的な飢餓状態が襲います。
人間と牧羊犬を欺いて羊を襲おうと計画しますが、計算外のハプニングで家族にさらなる危険が…。
母オオカミと6匹の子オオカミたちのイタリアからスイスまで1300キロに及ぶ旅路。
その先には、いかなる結末が待っているのか?BBCのカメラが母オオカミと子オオカミたちの姿を 追います』BS朝日 地球大紀行再放送より引用
「地球大紀行」は、「コトの本質」を書いた自然科学者、松井考典氏の企画、監修による1987年に始まった、地球、生命、人間、宇宙に関する壮大なシリーズドキュメンタリー番組であるが、「WILD NATURE 地球大紀行」は、BS朝日が放映する、英国BBC制作のオリジナルシリーズである。
狼のつがいのオスは、自分たちの獲物を狙う熊と闘い瀕死の重傷を負う。メスは最後までオスに寄り添い、添い遂げる。オスを置いて逃げることはしない。
オスが死ぬと、メスは群れの中に自分の居場所うなくなり、群れに帰ることはできない。ここからメスの、零下数十度の厳寒のアルプスを1300キロを移動する野生の生命力の強靭さを魅せる。
野生とは何か。一つには、闘う本能である。生命そのものの中に内包する根源的な生き延びる生命力である。
畳の上で人間に飼われる猫はネズミを捕らなくなる。犬も歯槽膿漏になるという。
何でも手に入る文明や環境の中で、ぬくぬくと生きている人間たちは、野生の生命力を失ってゆく。
生命のもう一つの側面、理性という、愛、貢献、連帯、犠牲等々も希薄になり、野生と理性のバランスが崩れてゆく。
人間社会は、今、やわな様相を呈している。子殺し、親殺し、煽り運転、等々を見るがいい。他者も同じ命や正義を生きていることを忘れる。
闘争力も、進化も、競争力に勝ち抜く意欲すら失われてゆく。チコちゃんではないが、ぼーっと、ぬくぬくと生きてんじゃねえよ、、である。
吉野弘さんは「生きていることの懐かしさ」と言った。命が持つ他者との一体感であろうか。
他者を認めつつ、フェアに闘うことを忘れる。格差社会を嘆くばかりである。
かって、子供たちは、野山や原っぱを駆け巡り、遊びや喧嘩に明け暮れていた。仲間たちには、面倒見のいいガキ大将がいてそれなりに統率がとれていた。
今、都会では、駆け巡る野山も原っぱも無く、ガキ大将もいない。ぶつかり合い、取っ組み合いの遊びと喧噪の中から自分を主張する場がなくなってしまった。
大自然の中から生き延びる知恵を学び取っていたが、今は草食系などという、喧嘩も遊びもしない、ひ弱な男子が多くなったと聞く。男らしさ、女らしさが薄れてきたのだろうか。”ひとの匂い”が失われたのだろうか。
宗教家でありながら、実社会に身を投じ活動する体験的哲学論者、町田 宗鳳氏が提唱する、 「野性の哲学」がある。
逞しく生き抜く力は、自己の中にある野性の力である。癒しは、外ではなく、自己の内にあるものである、と言う。
実社会を演釈出来ない学問、或いは、宗教は、その存在価値を失う。生きてゆくために必要なことは、癒しでも、救済でも、権力でもなく、他者を思いつつ、家族を、国を、世界の友を背負い、生き抜く強さなのであろうか。
町田 宗鳳氏は、アメリカ暮らしの実体験から、アメリカ社会の底力には、未だに狼の逞しい野生の匂いがするという。
ニューヨーク、マンハッタンには、世界の1%にも満たない富裕層、セレブ達の超高級住居群が林立し、ブロンクスなどの極貧層、ホームレスと対峙しているという。
弱者救済などという行儀のいい理屈は通らない、まさに競争社会の勝ち組と負け組がはっきりしているという。
狼の野生の本能に学ぶべき、競争心、闘争心むき出しの社会であろうか。
町田宗鳳ホームページ
https://www.arigatozen.com/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BA%E7%94%B0%E5%AE%97%E9%B3%B3
参考図書 「野性」の哲学―生きぬく力を取り戻す』(ちくま新書、2001年)
my challenger's log 一冊目は、
こちら
http://mwainfo.blog.so-net.ne.jp/
より閲覧願います。
野生の狼の強靭な生命力(WILD NATURE 地球大紀行)
『野生のオオカミ母子 厳冬のアルプスを生き抜く
イタリア・アルプスで命を落とした一匹のオスのオオカミ。
ボスであったそのオスを失ったメスのオオカミは、群れを追われます。
彼女には生きる理由がありました。彼女のお腹には6匹の小さな命が宿っていたのです。
たった独り、アルプスの厳しい自然の中で出産をし、捕食者たちから身を護り、獲物を狩り、子供た ちを育てなければなりません。
凍てつく雪と暴風の中で、危機的な飢餓状態が襲います。
人間と牧羊犬を欺いて羊を襲おうと計画しますが、計算外のハプニングで家族にさらなる危険が…。
母オオカミと6匹の子オオカミたちのイタリアからスイスまで1300キロに及ぶ旅路。
その先には、いかなる結末が待っているのか?BBCのカメラが母オオカミと子オオカミたちの姿を 追います』BS朝日 地球大紀行再放送より引用
「地球大紀行」は、「コトの本質」を書いた自然科学者、松井考典氏の企画、監修による1987年に始まった、地球、生命、人間、宇宙に関する壮大なシリーズドキュメンタリー番組であるが、「WILD NATURE 地球大紀行」は、BS朝日が放映する、英国BBC制作のオリジナルシリーズである。
狼のつがいのオスは、自分たちの獲物を狙う熊と闘い瀕死の重傷を負う。メスは最後までオスに寄り添い、添い遂げる。オスを置いて逃げることはしない。
オスが死ぬと、メスは群れの中に自分の居場所うなくなり、群れに帰ることはできない。ここからメスの、零下数十度の厳寒のアルプスを1300キロを移動する野生の生命力の強靭さを魅せる。
野生とは何か。一つには、闘う本能である。生命そのものの中に内包する根源的な生き延びる生命力である。
畳の上で人間に飼われる猫はネズミを捕らなくなる。犬も歯槽膿漏になるという。
何でも手に入る文明や環境の中で、ぬくぬくと生きている人間たちは、野生の生命力を失ってゆく。
生命のもう一つの側面、理性という、愛、貢献、連帯、犠牲等々も希薄になり、野生と理性のバランスが崩れてゆく。
人間社会は、今、やわな様相を呈している。子殺し、親殺し、煽り運転、等々を見るがいい。他者も同じ命や正義を生きていることを忘れる。
闘争力も、進化も、競争力に勝ち抜く意欲すら失われてゆく。チコちゃんではないが、ぼーっと、ぬくぬくと生きてんじゃねえよ、、である。
吉野弘さんは「生きていることの懐かしさ」と言った。命が持つ他者との一体感であろうか。
他者を認めつつ、フェアに闘うことを忘れる。格差社会を嘆くばかりである。
かって、子供たちは、野山や原っぱを駆け巡り、遊びや喧嘩に明け暮れていた。仲間たちには、面倒見のいいガキ大将がいてそれなりに統率がとれていた。
今、都会では、駆け巡る野山も原っぱも無く、ガキ大将もいない。ぶつかり合い、取っ組み合いの遊びと喧噪の中から自分を主張する場がなくなってしまった。
大自然の中から生き延びる知恵を学び取っていたが、今は草食系などという、喧嘩も遊びもしない、ひ弱な男子が多くなったと聞く。男らしさ、女らしさが薄れてきたのだろうか。”ひとの匂い”が失われたのだろうか。
宗教家でありながら、実社会に身を投じ活動する体験的哲学論者、町田 宗鳳氏が提唱する、 「野性の哲学」がある。
逞しく生き抜く力は、自己の中にある野性の力である。癒しは、外ではなく、自己の内にあるものである、と言う。
実社会を演釈出来ない学問、或いは、宗教は、その存在価値を失う。生きてゆくために必要なことは、癒しでも、救済でも、権力でもなく、他者を思いつつ、家族を、国を、世界の友を背負い、生き抜く強さなのであろうか。
町田 宗鳳氏は、アメリカ暮らしの実体験から、アメリカ社会の底力には、未だに狼の逞しい野生の匂いがするという。
ニューヨーク、マンハッタンには、世界の1%にも満たない富裕層、セレブ達の超高級住居群が林立し、ブロンクスなどの極貧層、ホームレスと対峙しているという。
弱者救済などという行儀のいい理屈は通らない、まさに競争社会の勝ち組と負け組がはっきりしているという。
狼の野生の本能に学ぶべき、競争心、闘争心むき出しの社会であろうか。
町田宗鳳ホームページ
https://www.arigatozen.com/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BA%E7%94%B0%E5%AE%97%E9%B3%B3
参考図書 「野性」の哲学―生きぬく力を取り戻す』(ちくま新書、2001年)
2020-01-26 12:09
nice!(273)
明けましておめでとうございます [社会]
皆様方のいつも温かいご支援を感謝いたします。
my challenger's log 一冊目は、
こちら
http://mwainfo.blog.so-net.ne.jp/
より閲覧願います。
皆様、新年あけましておめでとうございます。
新しき年、稔り多き年、健康である年をお祈りいたします。
本年も相変わりませずよろしくお願いいたします。
門松は 冥土の旅の 一理塚
めでたくもあり めでたくもなし
一休禅師の正月を詠んだ一句である。
60兆個の細胞が整然と秩序だって組み込まれ生まれた命は、輝かしい未来に向かい歩み始めるが、たどり着く先は、死である。
これは、宇宙のさだめ、エントロピー増大の法則を免れない。
命がけ、死に物狂い、と死と表裏一体でなければ、生きていることの充実感、使命感は達成されないであろう。
松井考典 理学博士は、考えるとは、「事の本質」見抜くことだという。
松井氏は、地球に海がなぜあるのかを20年以上も考え続けたという。
海がなぜあるのか、命がなぜ海から生まれたのか、地球はどうしてできたのか、等々が、 ある日、突然ひらめいたという。
椰子の実
名も知らぬ 遠き島より
流れ寄る 椰子の実一つ
故郷の岸を 離れて
汝(なれ)はそも 波に幾月
遠い日に、海辺の砂浜で、どこからともなく聞こえてきたのは、あの懐かしい唄と渚のざわめきであった。
三木成夫氏の「胎児の世界」によれば、
30億年も前、人類の原初の生命体は、海から陸へ上陸する前の渚で暮らした太古の生命記憶を持つという。
母の胎内で聞く羊水の音の記憶は、まさにこの渚のざわめきだという。
母親の胎内で赤ちゃんを育む羊水は、ミネラルバランスから見るとその組成は太古の海水とよく似ているといわれる。
「この地球上の生命が誕生したのは、30億年以上も前の海の中からである。生命が陸に上陸する前に、渚に暮らしていた時代に、生命体に月のリズムが刻まれた」のだという。
潮の満干は、人間の生命、特に母体とは密接に関係しているらしい。もうひとつ受け継ぐのが、体内時計である。 概日リズムの体外時計が、一日24時間に対して、生命の成長と老化を司る人間の体内時計は25時間であるという。この1時間の差がまた宇宙の神秘を秘める。
この1時間のズレは、朝の目覚めで、朝日を浴びることで24時間にリセットされる。リセットされない生活が長く続くと、夜と昼が逆転し、不眠症など心身のリズムとバランスが崩れ、体調不良になるという。
母親の胎内で胎児は、十月十日、絶え間なく響く血潮のざわめき、あの海の潮騒を聞いて育つ。
「生まれてまだ目もあかない赤ん坊が、何かを思い出したようにニッコリ笑ったりするのを、わたしたちはいつも見ている。それはほかでもない、母の胎内で見残したそのような夢の名残りを、実際見ているのだ」という。
「母の胎内で見残した夢の名残を見ている」という、壮大な生命誕生の遥かな記憶と神秘の物語である。
(胎児の世界 三木 成夫 著 より抜粋)
海辺の砂浜で、潮風と波のざわめきに身をゆだねれば、遠い太古の記憶、母の胎内で聴いた子守唄、渚のざわめきが甦る。
青い波の地平からやってくる頬を過ぎ行く潮風により、心身共にリフレッシュされるのかも知れない。
新しき年、輝くいのちへ、感謝の年であることを願います。
参考図書

my challenger's log 一冊目は、
こちら
http://mwainfo.blog.so-net.ne.jp/
より閲覧願います。
皆様、新年あけましておめでとうございます。
新しき年、稔り多き年、健康である年をお祈りいたします。
本年も相変わりませずよろしくお願いいたします。
門松は 冥土の旅の 一理塚
めでたくもあり めでたくもなし
一休禅師の正月を詠んだ一句である。
60兆個の細胞が整然と秩序だって組み込まれ生まれた命は、輝かしい未来に向かい歩み始めるが、たどり着く先は、死である。
これは、宇宙のさだめ、エントロピー増大の法則を免れない。
命がけ、死に物狂い、と死と表裏一体でなければ、生きていることの充実感、使命感は達成されないであろう。
松井考典 理学博士は、考えるとは、「事の本質」見抜くことだという。
松井氏は、地球に海がなぜあるのかを20年以上も考え続けたという。
海がなぜあるのか、命がなぜ海から生まれたのか、地球はどうしてできたのか、等々が、 ある日、突然ひらめいたという。
椰子の実
名も知らぬ 遠き島より
流れ寄る 椰子の実一つ
故郷の岸を 離れて
汝(なれ)はそも 波に幾月
遠い日に、海辺の砂浜で、どこからともなく聞こえてきたのは、あの懐かしい唄と渚のざわめきであった。
三木成夫氏の「胎児の世界」によれば、
30億年も前、人類の原初の生命体は、海から陸へ上陸する前の渚で暮らした太古の生命記憶を持つという。
母の胎内で聞く羊水の音の記憶は、まさにこの渚のざわめきだという。
母親の胎内で赤ちゃんを育む羊水は、ミネラルバランスから見るとその組成は太古の海水とよく似ているといわれる。
「この地球上の生命が誕生したのは、30億年以上も前の海の中からである。生命が陸に上陸する前に、渚に暮らしていた時代に、生命体に月のリズムが刻まれた」のだという。
潮の満干は、人間の生命、特に母体とは密接に関係しているらしい。もうひとつ受け継ぐのが、体内時計である。 概日リズムの体外時計が、一日24時間に対して、生命の成長と老化を司る人間の体内時計は25時間であるという。この1時間の差がまた宇宙の神秘を秘める。
この1時間のズレは、朝の目覚めで、朝日を浴びることで24時間にリセットされる。リセットされない生活が長く続くと、夜と昼が逆転し、不眠症など心身のリズムとバランスが崩れ、体調不良になるという。
母親の胎内で胎児は、十月十日、絶え間なく響く血潮のざわめき、あの海の潮騒を聞いて育つ。
「生まれてまだ目もあかない赤ん坊が、何かを思い出したようにニッコリ笑ったりするのを、わたしたちはいつも見ている。それはほかでもない、母の胎内で見残したそのような夢の名残りを、実際見ているのだ」という。
「母の胎内で見残した夢の名残を見ている」という、壮大な生命誕生の遥かな記憶と神秘の物語である。
(胎児の世界 三木 成夫 著 より抜粋)
海辺の砂浜で、潮風と波のざわめきに身をゆだねれば、遠い太古の記憶、母の胎内で聴いた子守唄、渚のざわめきが甦る。
青い波の地平からやってくる頬を過ぎ行く潮風により、心身共にリフレッシュされるのかも知れない。
新しき年、輝くいのちへ、感謝の年であることを願います。
参考図書
 | 価格:770円 |
2020-01-03 12:08
nice!(248)